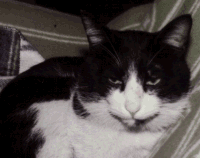|
猫屋敷クロニクル 3
XV
暦をチビくろ発見の日に戻す。
ぎーぎー怪音を発して肉球まで黒い子猫を持ち帰ったとき、よたろうは、5年ほどの年季を経て、まったりとした家猫ライフを満喫していた。
彼は、成長期にお岩という猫族の同胞と暮らしたせいか、いくぶん猫社会の一員という自覚が育っていた。つまり、人の手で、一人っ子状態で可愛がられ育った猫の場合、飼い主に対する独占欲が強く、同胞への了見はおおむね狭い。私の観察では、雌猫にその傾向が強いと思われるのだが、新規に子猫を拾ってきて世話を始めると、たちまち嫉妬に駆られて、新参者をいびりにかかる。三文小説の小姑根性は猫にもある。
ところが、よたろうのココロは海より広く、情け深さは底が抜け落ちていた。
まず、あの、食欲の権化のよたろうが、チビくろのエサに手出ししなかった。それどころが、自分の皿にチビが頭を突っ込んでも腹を立てず、順番を譲って見守った。
さらに、何を勘違いしたか、乳をほしがる子猫に、授乳を始めた。
日常、立派なきんたま袋を見せびらかせ往来を闊歩しながら、なぜ、ここにきて「授乳」なのか。母性と父性は相互乗り入れありなのか。こんなこと歴史上前例あることなのか。我々人間の混乱ととまどいを尻目に、よたろうは横ばいに寝転がって、来る日も来る日も大きな腹をチビくろに供した。疳の強いチビに朝昼晩と食らいつかれて、よたろうの腹の毛は次第に抜け落ち、赤い皮膚が楕円形に露出した。たいこ腹に細い手足の子猫がすがりつき、無心に乳を求める姿はまさに母子のそれであったが、子が強引に吸い付いたところで、偽の母から一滴の乳も出るわけはなく、代わりに血が滲んで出てくるという有様だった、しかし、よたろうは、我が身の痛さより、子猫への母性愛を優先させ、けなげに育児に励んだ。捨て身の愛はまったく無駄だったがそこに一種の感銘はあった。
しかし、両名の間に親離れ子離れの契機が永遠に訪れなかったのは誠に遺憾である。チビくろが長じるにつれ、二匹の関係は、次第に暑苦しい様相を呈し始めた。
XVI
チビくろの体格は、またたくまに、よたろうを凌駕した。その逞しさは前述の通り、北斗の拳に登場する極悪人の如しである。よたろうは、チビに比べれば縫いぐるみのように牧歌的だったが、体積に関して言えば枕一個分は優にあった。この二匹がTの字形に密着して伸び広がると、床の上の相当面積を覆って、通行にかなりの注意を要した。
よたろうは、夏場など風通しのよい場所を選んで、ぼてっと砂袋のように横たわり、まなこを薄く開いて、チビくろのなすがままに任せていた。チビが飽きるまで姿勢を崩すことはなかった。
時たま、チビが力の加減を間違えて牙が身に食い込むと、よたろうは「ぎゃん」と叫んで立ち上り、脱兎の如く駆け出すチビを追いかけて廊下の隅に追いつめ、お仕置きに及んでいた。その勢いといったら、炊事の最中、その足下に2匹が突っ込み、あおりを食らって包丁を握ったままふっとばされるほどであった。これは危険この上なく、また、取っ組み合って巨大な団子と化し、転がりながら互いの肩口に食いつく二匹は命を奪いあわんばかりのすさまじい形相なのだが、所詮は痴話喧嘩なので、仲裁に入る気もしない。
喧嘩に飽きると、団子状態をほどいてそれぞれ立ち上がり、周囲をのそのそと歩き回って「おやつ、くれ」とせがんだり、二匹で牛乳を茶碗一杯飲み干したり、トイレに行ったり、30分もすると、また元の場所でT字形に睦み合い、至福の時間を過ごすのだった。
XVII
よたろうとチビくろは、このように良好な関係を保ち続けた。猫同士の仲が良いことは、一つ屋根に暮らす家族として喜ばしい。ただ、何年経ってもチビの人に対する攻撃性は後退することがなかった。
一度だけ、チビくろが長い時間、静かに膝に抱かれていたことがある。
その日、夕食の後かたづけを終えた台所で、新聞を読もうと椅子を引いたら、チビが先に座っていた。抱き上げて膝の上に載せ替え、夕刊を広げた。彼は、耳の後ろや肉球を触られても怒らず、逆にこめかみで押し返して甘えた素振りを見せた。1時間ばかり、そうしていたと思う。活字に飽きて、席を立つときに、そっとチビを床におろそうとすると、彼は、まだ甘え足りないと抵抗した。珍しいことだったので、記憶に残った。私は冷蔵庫を開けて、詫び代わりに牛乳と夕食の残り物を猫の皿に出し、そのまま自室に引き上げた。
翌朝、チビくろの姿は家から消えていた。
XVIII
相棒が逐電したあと、よたろうは暫くつまらなそうな顔で暮らしていた。腹の丸はげには徐々に産毛が生えそろい、やがて純白の被毛が再生した。食べて、寝て、遊ぶ生活を淡々とこなした後、よたろうは、チビの時と同じく、不意に姿を消した。
二匹の猫は相前後して失踪したが、感触が不思議に類似していた。よたろうも姿を消す前夜、チビと同じく、名残を惜しむように、抱かれた腕にしなだれかかって、長い間、喉を鳴らしていた。
名残を惜しむ、という解釈が人間的観点に偏りすぎているのは分かっている。猫の真意など、もとより、掴みようがない。でも、少なくとも彼らは、自身が翌日家を出ることを知っていた。それは自分の意志であったかもしれないし、逆らいがたい猫の世界の条理に従ったのかもしれない。ともかく、二匹は満ち足りた表情をを印象づけた直後、何不自由ない生活を捨てて出ていった。そして、二度と家に戻らなかった。
よたろうが家出した後、私はれんれんと帰りを待ち続けた。夜、外で鈴の音が鳴ると、目を覚まして窓を開け、闇に目を凝らして名前を呼んだ。首輪の鈴を鳴らすのは近所の白猫で、呼び声に応じず、毎夜行き過ぎた。
雨音の激しい湿った日は、要領のわるいバカ猫の、濡れそぼった姿が想像された。
風がうなる真冬の明け方には、一層悶々とした。寒がりのバカ猫が、何を好んで出ていったのかと、恨み言を呑み込んだ。
カボチャを煮ると、口の周りを橙色に染めたバカ面が思い出された。本当にバカモン、と思った。
人の親は逆縁に遭うと、仏となった子の歳を数えるという。人と猫を同列にしては憚りがあるが、私も心の中で居なくなった猫の年齢を数えた。拾ってきた年から勘定して猫の平均寿命を過ぎた頃、ようやく、もう戻らない、戻りようがないと諦めた。

XIX おまけ
よたろう失踪の日から暫くして、近所のカメラ屋から現像に出していたフィルムが戻ってきた。36枚のプリント写真を順に繰っていくと、中によたろうの姿が写ったものが1枚あった。当時、父は買ったばかりのニコンの一眼レフで、はにかみ屋の猫たちを盛んに追い回していたのだ。
よたろうは、例の雀や蛙の埋葬場所である柿の木の根もとに、ひとり佇んでいるところを、物陰からフォーカスされていた。
真横に向いたその姿は、あごを引き、前足をつっぱり、不自然に腰を浮かせていた。長く形のいいシッポは後方に向けて弓なりに反り返り、一種の緊迫状態にあることを表していた。それは、紛れもなく、力みの姿勢であった。彼は一個の生命体として、健康の証を今まさに産みに落とさんと、全神経とエネルギーを括約筋に集結させているところであった。
こんな身も蓋もない瞬間を、目撃されただけでも心の痛手であるのに、レンズで狙われ映像とされてしまっては、猫といえども立場はなく、さぞ悔し涙にくれたに違いない。
よたろうの失踪はあまりにも唐突で心当たりが皆無であったので、残された人間たちは理由付けを求めた。そこへ現れた一枚の写真は格好の材料となった。よたろうは、脱糞の瞬間を写真に撮られて絶望し、憤慨の涙にむせびつつ家を飛び出してしまったのだ。むべなるかな。悲劇の原因は、この写真に発していたのだ。
このストーリーは失踪の説明として一応の形になっていたので、人間たちに好んで採用された。こんな詮ない噂を繰り返しているうちに、聞き耳を立てて猫が戻ってくるさ、という期待もあった。
結局、待ちぼうけを食ったまま、時間が経ち、写真が残って、この猫と過ごした日々を思い出すよすがになっている。
これが、バカ猫が置いていった最後のエピソードになる。
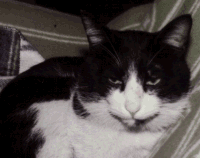
よたろう、ごはんやで。
うにゃ。
|