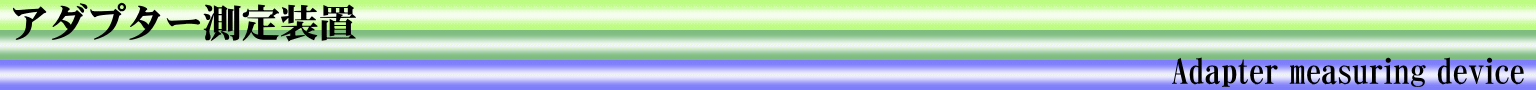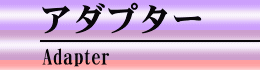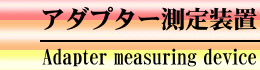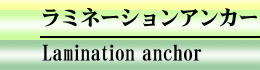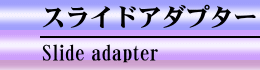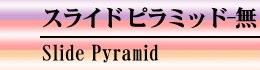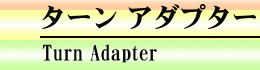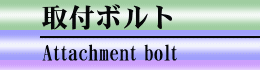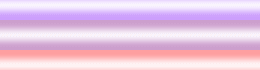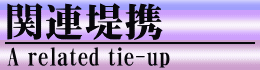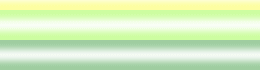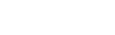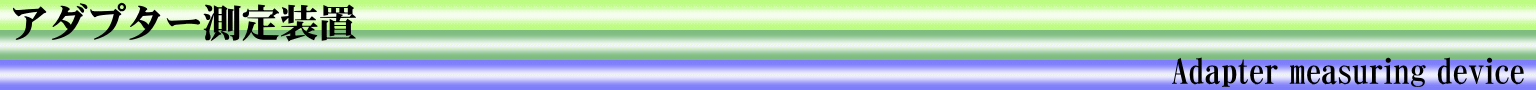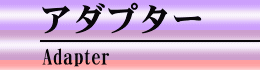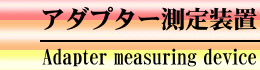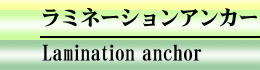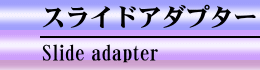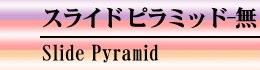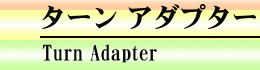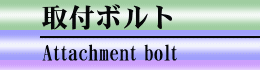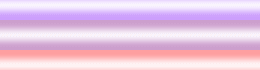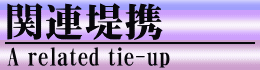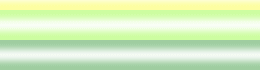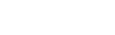(書誌+要約+請求の範囲+実施例)
| 【発行国】 |
日本国特許庁(JP) |
図3
 |
| 【公報種別】 |
公開特許公報(A) |
| 【公開番号】 |
特許公開2011-50514 |
| 【公開日】 |
平成23年3月17日(2011.3.17) |
| 【発明の名称】 |
義足組み立て用の測定装置 |
【国際特許分類】
A61F 2/62 (2006.01) |
【FI】
A61F 2/6262 |
| 【審査請求】 |
有 |
| 【請求項の数】 |
4 |
| 【出願形態】 |
OL |
| 【全頁数】 |
11 |
| 【出願番号】 |
特許出願2009-201067 |
| 【出願日】 |
平成21年8月31日(2009.8.31) |
| 【出願人】 |
|
| 【識別番号】 |
508197572 |
| 【氏名又は名称】 |
小西 幸夫 |
| 【住所又は居所】 |
新潟県長岡市青葉台5-4-1 |
| 【代理人】 |
|
| 【識別番号】 |
100091373 |
| 【弁理士】 |
|
| 【氏名又は名称】 |
吉井 剛 |
| 【代理人】 |
|
| 【識別番号】 |
100097065 |
| 【弁理士】 |
|
| 【氏名又は名称】 |
吉井 雅栄 |
| 【発明者】 |
|
| 【氏名】 |
小西 幸夫 |
| 【住所又は居所】 |
新潟県長岡市青葉台5-4-1 |
【テーマコード(参考)】
4C097
|
【Fターム(参考)】
4C097 TA05 TB17 |
【要約】
【課題】本発明は、従来にない作用効果を達成する画期的な義足組み立て用の測定装置を提供することを目的とする。
【解決手段】義足Fにおける前記上側構造部1に対する前記下側構造部2の適正位置を測定するものである。
【選択図】図3
【特許請求の範囲】
【請求項1】
身体に装着される上側構造部及び該上側構造部に連結され下端部に接地部を有する下側構造部のいずれか一方に突状部、他方に凹状の被嵌連結部が設けられ、前記突状部にはリング部材が設けられ、前記突状部はこのリング部材のリング孔内に配設され、前記リング部材の周面部に設けられた貫通孔には前記リング孔内の前記突状部を支持する支持部材が設けられ、前記リング部材は前記被嵌連結部内に螺着嵌合されるように構成された義足における前記上側構造部に対する前記下側構造部の適正位置を測定する測定装置であって、一端に前記被嵌連結部に螺着嵌合される螺着嵌合部を有し、他端に孔を有し、この孔の周囲に角度メモリが設けられた基体と、一端に摘子を有し、他端に前記孔に嵌入される嵌入部を有し、前記摘子の周囲に前記角度メモリを指示するメモリ指示部と基準位置を指示する基準指示部とが設けられた回転体とから成り、前記角度メモリのうちの基準角度メモリは、前記螺着嵌合部に形成される螺子溝の端部を基準として設けられていることを特徴とする義足組み立て用の測定装置。
【請求項2】
請求項1記載の義足組み立て用の測定装置において、前記角度メモリは、前記回転体の回転角度を示すものであって、前記基準角度メモリから少なくとも90度までの範囲において所定角度毎にメモリが設けられているものであり、また、前記基準指示部は1つであり前記メモリ指示部は3つであり、これらは90度の間隔をおいて設けられていることを特徴とする義足組み立て用の測定装置。
【請求項3】
請求項1,2いずれか1項に記載の義足組み立て用の測定装置において、前記螺着嵌合部の嵌合長さは、この螺着嵌合部の先端面が前記被嵌連結部の底面に当接するまで螺動し得る長さに設定されていることを特徴とする義足組み立て用の測定装置。
【請求項4】
請求項1~3いずれか1項に記載の義足組み立て用の測定装置において、前記摘子にはローレット加工による滑り止めが施されていることを特徴とする義足組み立て用の測定装置。
【実施例】
【0026】
本発明の具体的な一実施例について図面に基づいて説明する。
【0027】
本実施例は、身体(切断脚の大腿断端部)に装着される上側構造部1(ソケット部)と、この上側構造部1に連結され下端部に接地部3(足部)を有する下側構造部2(下腿義肢部)とからなる義足F(大腿義足)の連結部8におけるリング部材6の貫通孔6bの適正位置を測定するものである。尚、この下側構造部2の上部には屈伸運動を可能にする膝関節として機能する周知構造の屈伸部15が設けられている。符号16はシリンダー装置である。
【0028】
先ずは本実施例に係る義足Fについて詳細な説明をする。
【0029】
義足Fは、上側構造部1と下側構造部2とを角度調整機能付きの連結部8を介して連結される。
【0030】
具体的には、この連結部8は、下側構造部2の上部に設けられる突状部4と、この突状部4に連結するリング部材6と、上側構造部1の下部に設けられリング部材6に被嵌連結する凹状の被嵌連結部5とで構成されている。尚、上側構造部1に突状部4を設け、一方、下側構造部2に被嵌連結部5を設けるようにしても良い。
【0031】
突状部4は、図2に図示したように下側構造部2に設けられる屈伸部15の上面に突設された適宜な金属製の四角柱形状体である。
【0032】
この突状部4は、4つの各周面がテーパー面4aとなるよう上端側程径大に形成されている。
【0033】
このテーパー面4aを設けることで、後述する支持部材7で支持せしめた際、突状部4の周面が単なる垂直面だった場合に比し、支持部材7の先端面が可及的に面当接し得ることになって常に安定した良好な角度調整が可能となり、しかも、突状部4の良好な抜け止め作用が発揮されることになる。
【0034】
リング部材6は、図2に図示したように適宜な金属製の部材で形成したものであり、前述した突状部4をリング孔6c内に配して囲繞し得るように構成されている。
【0035】
また、リング部材6の外周面には被嵌連結部5が螺着する螺子溝6aが形成されており、この螺子溝6aが形成される外周面に後述する貫通孔6bが開口するように構成されている。
【0036】
また、リング部材6には、等間隔に4つの螺子孔から成る貫通孔6bが形成されており、この貫通孔6bは、リング孔6cの内面とリング部材6の外周面に開口するように設けられている。
【0037】
この各貫通孔6bは、図8,9に図示したように外側開口部よりも内側開口部の方が上方位置となるように傾斜状態に設けられている。この各貫通孔6bの傾斜角は、後述する支持部材7の先端部7aが突状部4のテーパー面4aに面当接する角度に設定されている。
【0038】
また、各貫通孔6bには支持部材7が螺着される。
【0039】
この支持部材7は、図2に図示したように適宜な金属製の部材で形成した螺子棒体であり、支持部材7をリング部材6に螺着した状態で突状部4をリング部材6に配し、この状態でリング孔6c内の突状部4を各支持部材7の先端部7a同士で支持することで突状部4に対してリング部材6を連結することができる。
【0040】
この支持部材7を介して突状部4にリング部材6を連結する構造が角度調整機能を発揮することになり、上側構造部1と下側構造部2とが最適な角度で連結されるよう、突状部4をリング部材6に最適な角度で配し、この状態で各支持部材7を適宜な量だけ突出させて突状部4を支持することで、上側構造部1に対して下側構造部2を所望の角度で連結することができる。この際、貫通孔6bの外側開口部から突出する支持部材7の基端部を切除するが、この切除した面がリング部材6の外周面と面一となるように切除する。
【0041】
従って、この状態のリング部材6に後述する被嵌連結部5を被嵌連結させた際、この被嵌連結部5で各支持部材7の基端部7bが抜け止め状態で支承され該支持部材7は所定位置に保持されることになる。
【0042】
尚、支持部材7は貫通孔6bに螺着する構造に限らず、圧入係止する構造のものでも良いが、いずれにせよ脱着し得る構造が望ましい。
【0043】
また、リング部材6の先端面6A(上端面)は、リング部材6を被嵌連結部5に完全に螺着嵌合させた際、被嵌連結部5の底面5Aに当接する部位である。
【0044】
被嵌連結部5は、図2に図示したように適宜な金属製の部材で形成した断面円形状の凹状体であり、上側構造部1の下部に設けられている。
【0045】
また、被嵌連結部5の内孔には螺子溝5aが形成され、前述したリング部材6に螺着して被嵌連結し得るように構成されている。
【0046】
また、被嵌連結部5の底面5Aは、該被嵌連結部5にリング部材6及び後述する螺着嵌合部9を完全に螺着嵌合させた際、リング部材6の先端面6A及び螺着嵌合部9の先端面9Aが当接する部位である。
【0047】
また、被嵌連結部5は、所定箇所にスリット部5bが形成されて縮径可能に構成されており、このスリット部5bの対向端部間には該スリット部5bを締め付ける締め付け部材17が設けられている。
【0048】
従って、被嵌連結部5をリング部材6に螺着して被嵌連結した後、締め付け部材17を締め付け操作してスリット部5bの対向間隔を狭めることで、リング部材6に対する被嵌連結部5の堅固な連結状態が得られることになる。
【0049】
次に、本実施例に係る義足組み立て用の測定装置S(義足Fの連結部8におけるリング部材6の貫通孔6bの適正位置を測定する適正位置測定装置)について説明する。
【0050】
具体的には、一端に前記被嵌連結部5に螺着嵌合される螺着嵌合部9を有し、他端に孔12bを有し、この孔12bの周囲に角度メモリ11が設けられた基体12と、一端に摘子14Aを有し、他端に孔12bに嵌入される嵌入部14Bを有し、摘子14Aの周囲に角度メモリ11を指示するメモリ指示部13と基準位置を指示する基準指示部19とが設けられた回転体14とから成り、角度メモリ11のうちの基準角度メモリ11Aは、螺着嵌合部9に形成される螺子溝9aの端部9a’を基準として設けられている。
【0051】
基体12は、図3,4に図示したように適宜な金属製で形成した筒状体であり、この基体12の一端部周面には螺子溝9aが形成され、被嵌連結部5に螺着嵌合される螺着嵌合部9として構成されている。
【0052】
また、基体12は、図3,4に図示したように他端部に鍔部12aが形成され、この鍔部12aは螺着嵌合部9を螺動させる際の握持操作部として機能し、この鍔部12aの周面にはローレット加工による滑り止めが施されている。
【0053】
また、鍔部12aの端面にして孔12bの開口端部には凹部12cが設けられ、この凹部12cは後述する回転体14の摘子14Aを回転自在に配設する部位である。
【0054】
また、鍔部12aには角度メモリ11が設けられている。
【0055】
この角度メモリ11は、図3に図示したように鍔部12aの端面にして凹部12cの周辺部位に基体12の軸芯線(回転体14の回転中心)を角度中心として複数設けられている。
【0056】
この角度メモリ11を設ける際の基準となる基準角度メモリ11Aは、螺着嵌合部9に形成される螺子溝9aの端部9a’(始端)を基準として形成されている。
【0057】
具体的には、図3に図示したように鍔部12aの端面所定部位にして、基体12の軸芯線を通過し且つ螺子溝9aの端部9a’に接する面Xと同一平面上に位置する部位に、基準となる角度メモリ11を設けてこれを基準角度メモリ11Aとし、この基準角度メモリ11Aから90度毎に計3つのメモリ11Bが設けられ、更に、基準角度メモリ11Aと一のメモリ11Bとの間には5度ごとに角度メモリ11が設けられている。尚、この基準角度メモリ11Aと一のメモリ11Bとの間に設けられる角度メモリ11は5度ごとに限らず、1度ごとでも良く、また、角度メモリ11は鍔部12aの端面の全周に設けても良い。
【0058】
回転体14は、図3,4に図示したように適宜な金属製の部材で形成したものであり、基体12の凹部12c内に回動自在に配される摘子14Aと、この摘子14Aの基端部に設けられ基体12の孔12a内に回転自在に嵌入配設される嵌入部14Bとで構成されている。
【0059】
この摘子14Aは、連結部材14cを介して連結される回転部14bによって基体12に抜け止め状態に設けられ、この回転部14bと基体12の内面との間に配される発条18により基体12の凹部12cに圧接状態に設けられている。
【0060】
従って、この構成から摘子14Aの回転に際して抵抗を生じることになり、不意に回転体14が回転してメモリ指示部13で指標した角度メモリ11が分からなくなってしまうことを防止することができる。
【0061】
また、摘子14Aの先端部周面にはローレット加工による滑り止めが施されている。
【0062】
また、摘子14Aには角度メモリ11を指標するメモリ指示部13と基準位置を指示する基準指示部19とが設けられている。
【0063】
このメモリ指示部13は、図3に図示したように摘子14Aの周面にして角度メモリ11が形成される部位の近傍位置に90度ごとに複数(3つ)設けられており、また、基準指示部19(図3中の黒三角印)は1つ設けられている。
【0064】
従って、回転体14を任意の位置に回転させた際、メモリ指示部13のいずれか一つは必ず角度メモリ11を指標することになる。
【0065】
以上の構成から成る義足組み立て用の測定装置Sを用いた、義足Fの連結部8におけるリング部材6の貫通孔6bの適正位置を測定する方法について説明する。
【0066】
先ず、図5,6に図示したように上側構造部1に設けられた被嵌連結部5に螺着嵌合部9を螺着嵌合させる。この際、螺着嵌合部9の先端面9Aが凹状の被嵌連結部5の底面5Aに当接するまで完全に螺着嵌合させる。
【0067】
続いて、図7に図示したように回転体14を回転させて基準指示部19を義足装着者が望む方向、即ち、上側構造部1に下側構造部2を連結した際の該下側構造部2が向いて欲しい方向を基準指示部19が指すように合わせると、メモリ指示部13が角度メモリ11を指標する。
【0068】
この際、メモリ指示部13が指標する角度メモリ11が基準角度メモリ11Aから何度に位置する角度メモリ11であるかで、リング部材6の周面に形成される螺子溝6aの端部6a’(始端)から何度の位置に貫通孔6bを設ければ良いか判断できる。
【0069】
具体的には、図7に図示した場合では、メモリ指示部13は基準角度メモリ11Aから50度の位置の角度メモリ11を指標しており、これを基に図8に図示したようにリング部材6の周面に設けられる螺子溝6aの端部6a’から50度傾いた位置に貫通孔6bを設け、この本装置Sで得られた適正位置に設けられた貫通孔6bを基準に、90度ごとに他の3つの貫通孔6bを設けることになる。
【0070】
このようにして貫通孔6bが形成されたリング部材6を用いて上側構造部1と下側構造部2とを螺着嵌合させた際(リング部材6の先端面6Aが凹状の被嵌連結部5の底面5Aに当接するまで完全に螺着嵌合させた際)、下側構造部2が向いて欲しい方向を向いた装着状態となる(図9参照)。
【0071】
よって、本実施例によれば、歩行が良好に行える最適な装着状態が簡易且つ精度良く得られることになる。
【0072】
尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計し得るものである。
|